
2015年06月26日
お久しぶりです、こじょんのび7号です! 先日、医療に興味を持っている地元の高校生の方達が、文化祭の振替休日を使って上越総合病院に職場見学にいらっしゃいました! 皆さんそれぞれ指導医の先生に従って各診療科での外来見学などされ、昼食会を挟んで午後は研修医とのグループワークと盛りだくさんのスケジュールでしたが、どの方もとても真剣に参加していらしてました。その一生懸命な眼差しに、若いって良いな高校生は素敵だな、と私達の方こそとっても良い刺激を受けて、まだまだお手本には程遠いけれど、いつか医療の現場で再会を果たすことができたらその時は良い先輩になっていよう!と改めてモチベーションが高まりました。 部活に勉強に、習い事や恋愛に……今時の高校生はきっと毎日色々なことで忙しくされてると思うんです。そんな中で、医師という職業や地域の医療に興味を持って今回の体験学習に参加してくれたのがこじょんのびはとても嬉しかったです。 終わってから振り返ると、高校時代って勉強以外にもっともっと、今だからできる、今しかできない、みたいなことが沢山あった気がします。失敗を恐れずに意欲をもって、色々なチャレンジで高校生活を充実させてほしい、と老婆心ながら思います。 医療人は人に対する愛と勇気と情熱で出来てるからさ……と勝手に主張しているこじょんのびなのでした。 それにしてもやっぱり、高校生ってフレッシュで羨ましいな~。皆すっごくきらきらしてました、まる。

2015年06月09日
こんにちはー!新大出身、1年目こじょんのびの若竹です。先日、糸魚川で行われたCPVS(Clinical Physiiology of Vital Signs)に参加してまいりました。 入江聰五郎先生とインストラクターの皆様にはるばるお越しいただき、糸魚川総合の研修医と指導医に混じって、当院より1年目2名が受講してきました。 医師免許を手にしてまだ2か月の私たちはかなり緊張ぎみで糸魚川まで初めての出張をしてきましたが、入江先生の気さくな人柄とこじょんのびOBのインストラクターの先生方もいらしたおかげで、とても充実した2日間を過ごすことができました! 技術も経験もまだない私たちが救外で戦っていくために持てる武器は限られていますが、2日間で35症例(!)をシミュレーションし、今まで深く考えずにながめていた6つの数字に命が吹き込まれ、新しい鮮やかな視界に目の覚めるような思いです。 研修はまだ始まったばかりですが、すでに数えきれないほどの鮮烈な、日々の記憶でいっぱいです。見るもの聞くことのすべてを糧として、一歩ずつ前へと進んでいきたいです。
2015年05月25日
五月になれば、風が爽やか。田んぼが青空を映し、早苗がきらめく季節がやってきた。 われらがこじょんのびたちの様子はどうだろう。一年生はだいぶ白衣が似合ってきた。新しい環境にも慣れ、いよいよ研修も本格的である。その一方で、いろんなことを考え始める時期でもあろう。 「自分に知識が足りないことを、日々思い知らされています。」 「時間が足りなくて。朝から夜まで毎日忙しいです。早起き苦手なもんで。」 医療現場の大変さは、もちろん想像していたはずだ。だが、現実は思ったよりもはるかに複雑で、忙しい。ややもすると自分の能力に疑問符がつき、不安になる。 二年生はそろそろ研修終了後の進路のことを考えなければならない。初志貫徹で、道を決めた彼もいれば、迷っている彼女もいる。人と自分を比べてあれこれと考える。 どれも無理のない悩みである。だが、深刻になりすぎてもいけない。悩みは成長のための痛みでもある。自分ひとりで抱えないことが大切だ。友人や、信頼できる指導医など、話しやすい相手を探して気持ちを聞いてもらうとよい。話すだけで心が軽くなる。話しているうちに、自分の心の底を冷静に見つめることができるようになる。その頃には悩みも小さくなって、ひょっとしたらよい解決法も見つかるかもしれない。今年の一年生から、当院ではメンター制度を導入したが、これもきっと君たちを助けてくれるだろう。自分は一人ぼっちではなく、みんなが君たちを気にかけていることを忘れないでいてほしい。 先日レジナビに出かけた。都会の名だたる研修病院には学生が鈴なりだが、地方の病院は静かなものである。淋しいやら悔しいやらだが、そこは我慢。それにしても、君たちはどうやって研修病院や進路を決めるのだろう。 新潟県内の初期研修医の意識調査をしたアンケートがある。この春卒業した仲間が、研修中の本音を語ってくれている。 初期研修先を決めるうえで重視したポイントとしては、多い順に次のようである。研修プログラムが充実している、指導体制が充実している、施設・設備が充実している、症例が多い、先輩の評判が良い、地元に近い。 最も多い「研修プログラムの充実」でも、それを挙げた研修医の数は全体の半分以下で、他はおしなべて三割程度にすぎない。どうも決定的な理由が見当たらない。結局大切なのはイメージで、理由はそれを自分に納得させるために後づけしたものかもしれない。 うーん、と唸ってしまう。あたかも異性を好きになるときと似たプロセスで研修先が決まるのであれば、研修病院の努力にも限界があるからである。イケメンとノン・イケメンの差はなかなか埋まらない、でしょ(?)。 その一方で、研修を始めてから研修病院に望むこととして、彼らは次のようなことを挙げている(多い順)。 指導体制の充実、処遇・待遇の充実、外部(県外・海外)研修の充実、研修プログラムの充実。何だか研修病院を選んだ理由とかぶりますよね。プログラムや指導体制に期待して研修を始めたのに、それがいわば裏切られる結果になっているとも読める。 だとすれば、研修病院の努力のし甲斐もあるというものである。ノン・イケメンの病院であっても、親身の指導やプログラムの工夫でモテる可能性があるということだから。 さらにこんなデータもある。1/3の研修医は、大学卒業時に予定していた進路を、初期研修中に変更している。そうさせるだけの体験や出会いがあったということであろう。 やはり初期研修は、さまざなな可能性を秘めた、大切な時期に違いない。君たちに多くのチャンスを示し、たくさんのポジティブスイッチをオンにする。当院はそんな研修病院を目指しているのである。ともに励みましょう!

2015年05月12日
ブースに来てくれた医学生さん! 病院見学・実習お待ちしています。
2015年04月22日
待ちわびた桜の季節も瞬く間に過ぎた。年度末からの忙しい日々が一段落したところで、前回コラムからの出来事を振り返ってみる。 3月20日、臨床研修終了式。6名の二年生たちが無事研修を修了し、巣立っていった。後輩研修医や職員に向けて、心温まるスピーチを残してくれた。全員男性なので、昨年のように涙、涙という感じではなかったが(若干例外もいたようだ)、素直な言葉に心が動く。 「そうか、そんなことを考えていたのか。」 そう思わされることが多い。プログラム責任者として心を砕いてきたつもりだが、彼らのことをよく知らなかったことに気付く。やりがいがあったこと、達成感を感じたこと、楽しかったこと。ポジティブな経験もたくさんあったとは思うが、誰にも言えずに傷つき、悩み、迷いながら日々の研修を送っていたことがわかる。もっと話を聞いてあげればよかったと思う。いささかつらい時間である。 場所を移して、臨床研修上越糸魚川コンソーシアムの全研修医が集まって祝宴を開く。一言ずつ挨拶をしてもらい、記念品を手渡す。お酒が入れば懐かしい思い出がよみがえる。旅立ちを見送るのは、正直なところ淋しい。同窓会では元気な姿を見せてくれよ、そう伝えながら握手を重ねる。今後の成長と幸運を祈るばかりである。ありがとう。 4月1日、新入職員対面式。この日はすべてが新しい。今年もピッカピカのニューこじよんのびがやってきた。基幹型はフルマッチして6名、大学病院からのたすきがけが1名、合計7人のルーキーたちである。たすきがけの二年生も1名来てくれたので、一気に大所帯になった感じがする。 白衣に着られているような初々しい姿に、思わず声をかけたくなる。後輩ができて、新二年生の表情が引き締まっている。よろしくお願いします、という戸惑いがちな彼らの言葉に、もちろんだよと心の中で応える。 とはいえ、万事はこれからである。二年の間に、彼らを医者として独り立ちさせなければならない。多くの行動目標や経験目標をクリアさせ、修了まで後押ししてゆかなければならない。プログラム責任者としては、一年で一番気持ちが引き締まるときである。 当院では、研修に先立って、彼らルーキーにフレッシュマンセミナーというオリエンテーションを行っている。今年はその期間を二週間に延長し、コメディカル研修に近い内容のものにブラッシュアップした。 研修医の指導には、指導医だけではなく、他職種が関わらなければならない。いわゆるinterprofessional educationである。グラム染色、血液交差試験、心電図記録の仕方など、重要なスキルをここで体験する。ナースと一緒に、体位交換、排泄介助、血管確保、与薬などのナーシングスキルを実践する。ナースはとりわけ研修医にとって大切な教師である。感受性豊かな時期の経験が、今後の医師のキャリアの中で必ず生きてくるに違いない。快く協力してくれた看護部のスタッフはじめ、すべての職員に、心からお礼を述べたい。 皆にお世話になったからには、プログラム責任者たる小生も、体を張らねばなるまい。毎年小生が患者役になって、ルーキたちに患者さんへのアプローチを学習してもらっている。一昨年は急性虫垂炎、昨年は肺塞栓、今年は洞不全の患者を演じた。このプロセスを通じて、手際の良い問診、バイタルサインの解釈、身体診察の手順、問題リストや初期計画の作成など、診療のためのひととおりの手順を学んでもらう。一所懸命に考える彼らの姿が頼もしい。 いずれ小生が本当に病気になったとき、頼れるのは彼らである。すくすく成長してほしいと思う。サポートは惜しまない。これからずっと、一緒に学んでゆこう。

2015年04月18日
この春に医師国家試験に合格を果たし、4月よりここ上越総合病院にて臨床研修を行わせて頂いています。一日から数えて二週間余り、新人ナースさん達と一緒に学ぶオリエンテーションも終盤でいよいよ各科での病棟研修が始まって参りました。 初日は文字通り右も左もわからず(地域の中核病院の一翼を担っているため思わず迷子になる位大きくて沢山の施設があるんです!)緊張で肩がこわばって私達ですが、この頃は少しずつ新しい生活に慣れ、じょんのび先生にも「だんだん柔らかい表情になってきたね」と仰って頂けるまでになりました! 上越総合病院の優しく頼れる先生方や先輩研修医の先生、コメディカルの方、職員の方の温かな御支援のお蔭で充実した研修生活のスタートとなり、本当に嬉しく思います。 『衣食足りて礼節を知る』という言葉がありますが、こじょんのび風に言うと 『じょんのび足りて学びを知る』という感じでしょうか。 のびのびした研修をさせて頂く喜びを噛みしめると共に、患者さんへ医師としての責任を果たそうという自覚が芽生え身の引き締まる思いです。 もう一つ、じょんのび先生も折に触れて私達にお話しくださり、私も個人的に好きな言葉があります。 『患者さんから多くを学びなさい患者さんが君達の一番の先生なのだから』 大昔の偉大な名医ハリソン先生から脈々と受け継がれているこの言葉を、これからも忘れないようにしたいです。 上越地域の先生方、どうぞよろしくお願い致します!! 新米こじょんのび7名、短い期間ですが精一杯頑張ります!

2015年03月24日
3/20(金)に上越糸魚川コンソーシアム4病院で初期臨床研修を修了する研修医を送るセレモニーが開かれました。 研修を修了される先生方からは、上越地域での研修がとても充実していたと感謝の気持ちが多く聞かれました。 研修医の声は、後ほどお伝えします。 上越糸魚川コンソーシアム事務局

2015年03月24日
じょんのび先生とこじょんのび2名が東京が、全国から集まった医学生さんに当院の臨床研修について丁寧に説明してきました。 ブースに来られた方もそうでない方もぜひ一度、上越総合病院の見学実習に来院ください。 充実した病院見学をお約束します。 見学の申込みはホームページの病院見学申込サイトまたは、下記のメールアドレスへ直接どうぞ。 上越総合病院 教育研修推進室 梅澤真美子 rinsho-jimu@joetsu-hp.jp
2015年03月04日
慌ただしさに身をまかせ、お正月もバレンタンデーも過ぎ去って、はや三月になった。年をとると、光陰ジェット機のごとしである。 さて、前回のコラム以降の、研修医のためのイベントを振り返っておこう。 1月25日、糸魚川総合病院に出向いて、「診断戦略」の志水太郎先生のレクチャーに参加。これまでにはなかった切り口で診断に迫る、新鮮な内容であった。 2月1日、徳洲会奄美ブロック総合診療研修センターの平島修先生をお招きして、「上越糸魚川フィジカルクラブ」を開催。男子諸君はみんな裸になって、いい汗かいたねえ(笑)。 2月24日、亀田総合病院集中治療部の笹野幹雄先生の教育回診。今回はありがちな診断エラーをテーマにした症例を提示した。グループに分かれて活発なディスカッションができた。素晴らしいことだ。 1月31日、NPO法人日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)主催の基本的臨床能力評価試験を受験。当院の研修プログラムを評価する手段の一つとして、昨年から受験料病院負担で研修医諸君に受験してもらっている。小生も試験監督をしながら、一緒に問題を解いてみる。結構難しい。先日採点結果が届き、当院基幹型二年生の平均点は、試験に参加した全国の研修病院のうち、何と第四位であった! 望外の快挙である。まあ、問題の当たり外れもあるので、あまり喜ぶのもよくない。とはいえ、昨年は全体の中ごろだったことを思えば、大きな進歩である。 さて、イベントばかりが研修ではない。日々の積み重ねこそが基本である。半年ほど前から、彼らがERで経験した症例を取り上げて、イベントに招いているゲスト指導医にならって、上越総合病院版プチ教育回診を始めた。持ち回りで症例を準備し、プレゼンをしてもらう。今は小生が司会役で質問を引き出したり、ディスカッションをコーディネートしたりしているが、いずれこの役回りも後期研修医や二年生にやってもらおうと思っている。ともあれ、数をこなすうちに彼らのプレゼンの要領が良くなり、ツボを心得た意見が増え、正しい診断ができるようになってきた。継続は力なりである。加えて、取り上げた症例の問題点を「意識障害」とか「胸痛」とかのコンセプトに集約すれば、レポートを書くときの参考になる。良いことばかりである。今後も継続して、当院臨床研修の目玉にしてゆきたいものである。 3月は卒業の季節だ。今年は6人の基幹型二年生が初期研修を修了し、それぞれの後期研修に巣立ってゆく。4月からは入れ替わって6人の基幹型と1人の協力型の、ピッカピカの新人がやってくる。3月20日は修了式である。昨年は涙、涙だったが、今年の卒業生はどんなメッセージをわれわれに残してくれるだろう。後輩たちは、どんな気持ちでバトンを受け継いでくれるだろう。そしてわれわれ指導医・指導者たちは、彼らの足跡をこの病院のよき伝統に高めてゆかなければならない。考えなければならないことがたくさんあって、じょんのびしている時間がないのである(笑)。ともあれ、卒業生についてのメッセージは次回をお楽しみに。 最近面白かった本。トマ・ピケティ「21世紀の資本」-富が一部の人に集中し、経済格差が拡大していることを詳細なデータで示している。経済学書であるが、世界的ベストセラーである。医療の現場にいると、較差拡大の結果か、日常の生活に苦しんでいる人たちが急に増えてきたことを実感する。その背景にある資本主義の問題と、それをコントロールする民主主義への希望が描かれている。ちょっと勇気をもらった次第である。 ではまた、次回。
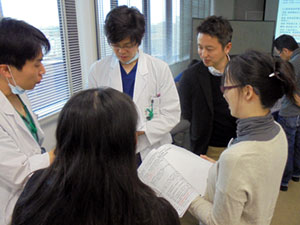
2015年03月03日
2月24日上越総合病院にて笹野幹雄先生の教育回診がありました。 笹野先生は全国的にも有名な亀田総合病院から上越に来られました。 今回の教育回診で取り上げられた症例は、誰にでも経験しうる症例で、非常に勉強になりました。 笹野先生は診断への道筋を考えるヒントや今回の症例だけでなく、様々な症例にも適応できる考え方のフレームワークを我々に授けて下さり、大変参考になりました。 このような機会に出会えたのは上越や糸魚川で研修をうけていたからであり、研修医として冥利に尽きると思います。今後は、先生に教えていただいた考え方を活かして、医療に取り組んでいきたいと強く思いました。 笹野先生、本当にありがとうございました。 上越総合病院 研修医2年目 井上 悟